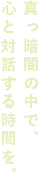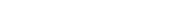DIALOGUE RADIO -IN THE DARK-
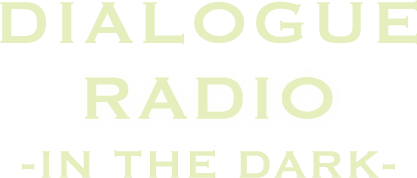
日曜の深夜。全てのしがらみから離れて
本当に「独り」になっている特別な時間。
人は誰もが不安や悩みを持っているはず。
この番組は、自分の心と対話することの大切さを伝え、
明日への活力を求める人への応援メッセージを
発信するラジオ番組です。
EVERY SECOND SUNDAY
25:00-26:00 ON AIR
MESSAGE
人は他人と比較してしまう生き物だと思います。
人より、恵まれていると喜んだり、
人より、うまくいかないと落ち込んだり、
SNSが生まれたことで、自分を誰かと比較する機会も増えてきました。
そんな今だからこそ自分の心と対話する時間を大切にしたいと思います。
何をしたいのか、何が悩みなのか、何に希望を持つのか。
その積み重ねが幸せを感じる近道なのではないかと思います。
幸せは、自分の心の中にある。
2024.07.14
GUEST

第73回のゲストは、萩原道秀さんでした
〜プレゼント〜
番組初となる著書、
『暗闇ラジオ対話集-DIALOGUE RADIO IN THE DARK-』を
番組をお聴きの方の中から2名の方にプレゼントします。
ご希望の方は、この番組のサイトにある
「MESSAGE TO STUDIO」の欄から
番組の感想をお書き添えの上、ご応募ください。
PHOTO
DIALOGUE
志村:今日は本当にありがとうございます。
萩原:こちらこそありがとうございます。
志村:「うりちゃん」っていうふうに呼ばせていただいてますけど、うりちゃんと私、出会ったきっかけっていつでしたっけ?
萩原:いつだったか・・・共通の大切なお友達のご紹介で、きいちゃん(季世恵さん)と初めて会ったのかな。
志村:はい。あのときに、今でも印象に残ってるんですけれども、帰り道をご一緒させていただいて、うりちゃんとお話をして、うりちゃんがお花のね、生け花の家元だってことを伺って、そこからお花のことをたくさんお聞きしたんですよね。あのときのお話が本当に素敵で、いつかあのお話をここでもいただきたいなと思って今日に至ったので、夢が叶って嬉しいです。
萩原:ありがとうございます。上手くお話できるかどうかわからないけど、よろしくお願いします。
志村:私もです、よろしくお願いします。そうなんです、うりちゃんのご活動というかお仕事は2つおありですよね。
萩原:はい。
志村:1つが先ほどお話したお花の、山村御流の家元をなさっていらっしゃる?
萩原:そうですね。
志村:あのう・・・特徴的な、私から見ると、野山に咲くお花を、とっても自然のままで生かされているお花を、4月に花展があって、私そこで拝見して、あのときもすごく感動したんですけど。
萩原:ありがとうございます。野山に咲く、野にある花をそのまんま生かしましょうっていうようなね、考え方なんだけれども、私の考え方としては、野山に咲いているお花ってもう無条件に美しいでしょ?それを自分の前にいただいてきて、それで生けるんだけれども、なんかお花ってそこで役割が変わってきてね、野山で咲いてる無条件に美しかったのが、人が手をすることによって、この生ける人とお花との対話というか会話?お花はどう生けられたいんだろう?とかね、それで人間の方は、どう生かしてあげれば美しく生けられるんだろう?とかね。そういうお花との対話というか、お花の力をもらって生かさしてもらってるっていう感じの生け花なんですね。
志村:そうですか、うーん。
萩原:そうすると、やっぱりご高齢の方が結構お花されてる方多いんだけれども、いつもおっしゃるのは、お花に力をもらってるっておっしゃるのね。それってやっぱり地べたから地球の力をもらってお花は生きてるし、人間もその全ての力をもらって生かされているわけで、その対話の中でどうやったらあなたは美しく生けられたいの?どうやったら生かしてあげられるの?っていうところの対話の中でのお花なのかなって。それが山村御流の特徴なのかなって自分で勝手にそういうふうにはね、思っているんですけど。
志村:あーそうなんですね。ものすごく自然で、野山に咲くお花って、なかなかこう、自然の世界をもう1回再現するのってなかなか難しいじゃないですか。それをそこにあったかのように、うりちゃんが生けてらしたんですよね。
萩原:なんか、お花の気持ちというか、心を、相手は話ができないからなかなか難しいんだけれども、読み取ってあげるっていうのかなぁ。お花って、この間きいちゃんが来てくださった花展で生けさせてもらってたのが、二輪草っていうお花なんだけど、
志村:白くてね、ちっちゃな。
萩原:そう、それはね、共通のお友達の私の大切なお友達に誘われて、ある場所で採集をさせていただいて、連れて行ってもらったところが一面の二輪草の群生してたのね。もうものすごい感動して、それで根からいただいて、一輪生けさせていただいて、あとはお寺の中庭に植えたんだけどね。なんか二輪層もそうだけれども、私の考え方なんだけど、人と似ているような気がしてね。なんか二輪草は最初の一輪目が咲いて、で、一輪目が数日経って元気がなくなってくると二輪目がだんだん元気になって咲いてきてね、一輪目は二輪目が咲くのを待っているようで、二輪目は一輪目がだんだんだんだん衰えてきたので、今度は自分の番かなと思って咲いてきて、お互いに思い合って咲いてるような気がして、それがすっごく可愛いなと思って、だからもう本当に人間もね、ちょっと相手のことを思いやるような気持ちが相手に伝わればね、もう争い事なんか無いだろうし、戦争なんかも無くなるのになっていつも思ってるんですけどね。
志村:あー、植物を触りながら、生かしながら、そんなことをお考えになっていらっしゃるんですね。まあ、花はね、植物は種から芽吹いて、そしてそこに存在するんだけれども、人間だけが花を愛でたりとか、そしてそれをまた生かそうとしたりとか、もしくは人に送ろうとしたりとかしますよね。自分の元気のためにお部屋に飾るとか、そういうふうな優しさを持ってるのにも関わらず、違う気持ちも来てしまうんですもんね。
萩原:そうね。やっぱりその、例えばお花を誰かにプレゼントしようとか、この花を持っていったら相手が喜ぶだろうなって、きっとお花を送る人ってみんな相手のことを想像しながら送ってあげると思うんだけれども、お花ってそこでもう人との関わりの中でお花の役割がそういう役割になってて、なんか面白いよね。お花だけで咲いているのと、人との関わりでお花が生かされてくるのと、感じが変わってきて面白いなって思うんだけどね。
志村:本当にそう思います。
萩原:なんか人間もそうだけど、1人だけじゃ何もできないところが、何かが加わると、何かの力になるっていうのとね、共通するようなところがあるような気がしてね、そういうところがすごく美しいなって思うのね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
志村:あのう、そういう感性・・・うりちゃんがお持ちの感性って、前からあるんですか?
萩原:どうなんだろうなー。あのう・・・んーなんかね、ものを見たりするときに、冷静にそういったものを見られるようになったのは、お坊さんになってからかもしれない。
志村:あー、そうですか。冷静に見ながら、そして情緒もものすごくおありで、そういうふうなことって、やっぱりお寺で過ごすお時間もあるんですかね。
萩原:うーん、あのね、お坊さんになってから、私おうちもお坊さんのおうちではないのでね、途中から僧侶のお話があって、僧侶になろうって決めたんだけどね、お坊さんって僧侶とか、ご住職とか、いろんな言い方があると思うんだけど、お坊さんって職業じゃなくてね、そういう生き方の人。
志村:あーそう・・・
萩原:ご職業だったら嫌だったら辞めればいいし、転職もできる。だけどお坊さんは、もう一生そういう人。だからお坊さんってそういう生き方の人をお坊さんって言うんだろうなって思ってるのね。それでそのお坊さんになってから2つだけいいことというか、以前の生き方と違ったなって思うことがあってね、1つは自分の心と向き合う力が身に付いたっていうか、何でも自分の心に問いてみる。これどうなのよって。そういうような感覚が生まれているのと、もう1つは、何でも自分のところに降りかかったこと、いろんなことがやっぱりみんな生きてるといろいろと自分の身に降りかかることがあると思うんだけど、それを引き受ける、自分のものとして引き受けて、考える。そういう強さは身に付いたかなっていうふうに思うね。そういうふうになりたいと思うし。
志村:うーん。先ほどおっしゃっていた、お坊さんになってからご自分のことを見つめることがきっと深まったんだと思うんですけど、それはお坊さんになる前となった後ではどのような感じの変化だったんですか?
萩原:うーん、あのね、コロナがすごく流行り出したとき、世間もみんなどうしようもなくなったときにね、東大寺の発案というか「正午の祈り」っていうのをやりましょうっていうのを新聞でちょっと見て、もう次の日にやりまーすって手挙げて連絡して、お仲間に入れていただいて始めたのね。
志村:正午、12時のお祈りですか?
萩原:そう、それでね、正午の祈りって言って、毎日12時に時間だけ決めてね、それは宗教、宗派、いろいろ問わず、場所も問わず、どこでもいいからコロナのウイルスの終息を願って、12時にみんなでちょっと手を合わせてお祈りしましょうよっていうようなね、そういうスタンスのお集まりというか、お約束なんだけどね、毎日毎日お寺にいないことも仕事であったんだけど、いるときには毎日12時に正午のお祈りをしてたのね。それって、うちのお寺は拝観をしてないので、大体1人か、まあ人がいれば数人で、毎日毎日終息を願って、それからお隠れになっちゃった方々のご冥福を祈りながらね、してたの。毎日やってて、でも1人でやってたんだけれどもね、場所も違うし、宗派もいろいろ違うし、宗教もみんな違うし、どこかで誰かが12時に一緒に手を合わせてるっていうね、そういう気持ちがものすごく自分の力に逆になって・・・なんていうか、感じてね、すごくもう1人じゃないんだなって、みんなで何とかならないかって言うような、うちは如意輪観音様をお祀りしているんだけれども、一生懸命一生懸命それをお唱えして、だけど、なっかなか聞いてくださらなくてね、2年半ぐらいかな、毎日やってて、やっとね5類になったけれども、でもそのときの気持ちって、やっぱりここに現実にいるのは1人だけれども、でも全国に一緒に同じ時間になにか1つのことをやってるっていうところが、ものすごくみんなの力になってるのかなって、で、お祈りするっていうことは、自分が安心することじゃないかなって思ったのね。今も自分のために、相手のためとか人のためとか、それからをお隠れになった方のために、もちろん浄土にね、何事もなくいっていただくためにお祈りをしてるんだけれども、それを介すとやはり自分に返ってくるというか、自分がお祈りさせてもらって、安心してみんなを導きたいっていうような気持ちに変わってくるのかなっていうふうに思うのね。
志村:あー、わかる気がします。お相手のことを思ったり胸を痛めているときは、そのお相手のことを祈るけれども、痛めている自分のこともその中に本当は入ってるわけですよね、きっとね。
萩原:そうそうそう、うんうんうん。
志村:うーん。あー、そうか、お坊さんになられて、そういう時間のこと、なんだろう、感じる、考える時間っていうのを、感じる時間とともにお過ごしになられるわけですね。静かな時間の中で。
萩原:そうね、やっぱり、なんていうのかな、今、闇の中にいてね、とても静かな中でお話させていただいてるんだけれども、やっぱりこういう時間って自分と向き合える時間になるのかなって思ってね。座禅もそうだけれども、やっぱり自分の心と向き合うことって、なかなか普通の生活だとできない、なかなかそういう時間が作れない環境の中にみんなあると思うんだけど、やっぱりちょっと落ち着いて、世の中の音に耳を澄ますっていうのかな、何にも聞こえないんだけれども、でもなにかこう・・・耳を澄ませて、何も考えない時間があると、心が落ち着くかなぁと、まあ私はいつもそうしてるんだけど、たった5分でもいいんだけどね。
志村:そうですねー。私いま、うりちゃんのお話をずっと伺っていて思い出したことがあったんです。私体が弱かったので、子供のときに入院するのが多かったんですね。で、痛いところがあるとか手術をするとかの前日なんかに、仏様や神様にお祈りするんですよね、子供ながらに。で、明日の手術成功しますようにとか、または痛いのが治りますようにって祈ってるんだけど、ふとね、自分のことを祈っていた時間から、あれ?お隣の病室の人も同じようになにかがあって入院してたんだなって思ったりとかしていて、その隣の人もって、だんだんだんだんイメージを起こしていくんですよね。そうすると、あ、きっと私のような人がいっぱいいて、明日手術の人もいて、もしくは手術を受けられない人もいて、みんな病気の方がここにいるんだなと思って、なんかお祈りがだんだん増えていくんですよ。そうすると病院の外にもお祈りが増えていって、なんかわかりますかね?
萩原:すごくよくわかる。
志村:こんなにいっぱいお祈りすることができるんだって思ったときに、それがね、さっき安心したっておっしゃっていたうりちゃんの気持ちがわかったというか思い出したんですけど、私がそこで祈ってる自分に安心したんですよね。
萩原:うん、うん、うん。そうそう、そうなのよね。だからなんか、お祈りって、やっぱ相手に、相手というかいろいろなことに対して願いをするんだけれども、でもそれを介すと、やっぱり自分の、なんていうの、心の安心のためにやってるのかなって、改めて考えるとね、そう思うかなー。
志村:そうですね、それはなにかちょっと不思議な感覚で、その見えない方と私は一体になるような気持ちになったりとか、なんかね、そんなふうで、大学病院に入院していたので、結構救急車も多いんですね。夜中とかね、でも怖いなって思うんじゃなくて、あ、無事でありますようにとか、治りますようにって思ってると、その方と私は横並びになってる感じで、そうすると、恐怖とか、うるさいなじゃなくって、ちょっとなんかね、仲間みたいな感じ。で、そういうのがあり続けることっていうのは、もしかすると、うりちゃんがおっしゃっていた最初のお話の平和に結びつくのかなって、ふっと思ったりしました。
萩原:あの、なんていうのかな・・・1人でやってるけど、いろいろなことを考えていくとね、同士のようにね、一緒に頑張りましょう!みたいなね、そんな気持ちになってくるんだよね。だからそれがやっぱり一言にお祈りとか祈願とかいろいろあるけれども、でもそれって神様や仏様を介して、自分の気持ち、心の安全もあるし、願うことでみんなが平和な優しい気持ちになればいいかなと思うよね。
志村:本当ですねー、うーん。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
萩原:なんかね、昔、障害持ってるところの施設に支援というか、そういうところで働いてたことがあったんでね、それで、私がいたところはね、超重度の知的障害の方たちの、なんていうのかな、通所施設だったの。それで、まあ介護福祉士としてそこにいたんだけれども、一番最初そこに行ったときにね、ものすごいもう半径1m以内に人を寄せ付けないみたいな、超重度な障害を持ってる人がいてね、その方はやっぱり多分人が怖い、自分になんかこう来るような気がするのか、それとあとは反射的に手が出てしまう、足が出てしまうっていうような感じの人だったのね。それで靴を履かすのも、もうみんな右往左往して大変なわけ。靴を下向いて履かせてると上から殴られたりとかね・・・(笑)なんかそんなような感じだったんだけど、でもね、ちょっと考えてね、その人結構お笑いの志村けんとかが好きでね、そのビデオとかを見せてるとすごく落ち着いてるみたいなところがあったのね。それでね、この障害というかあれをね、笑いに変えようかなと思って、例えば蹴飛ばされたら、わざとアイテテテテって言って転けてみたりとかね、そうするとね、笑うんだよね。そうするとだんだんね、蹴飛ばさなくなるの。殴られたらね、手を持ってね、頭でコッていう音を出したりするとね、笑うのね。で、毎日毎日その支援するっていうか、このみんなをね、どういうふうにしたら安心して暮らすことができるんだろうとか、どうしたらあれなんだろう、どうしたらあれなんだろうって、毎日毎日本当に、支援する側は考えてね。
志村:関わり方をね。
萩原:そう、関わり方をね。やっぱり支援する方も、なんだろう、その人たちを支援してあげようって思うのと、その人たちと一緒に飛んだり跳ねたりして心を1つにしてっていうか、通わせてね、支援していくのかっていうね、そこの線の違いで、その人たちの関わり方って変わってくるのかなって思ってね。だけど毎日毎日そうやってみんなのことを考えながら一生懸命サポートする側は考えるじゃない?でね、ある日ね、毎日毎日こんなもうどうしようどうしようってみんなでこうしようああしようっていうのが続いて、ちょっと考えたのはね、この1人ひとりの可能性って、なんかとってもここが引き出せれば、この人きっとすごいよねっていう人がたくさんいるのね。だけどそれを上手く引き出してあげられるかあげられないかでだいぶ違って、これってこの人たちって、人類の宝だなって本気で思ってね、本当に思ってるのね。すごいなんか宝物だなって。この人たちがいなければ、こういうふうに考えることもしないし、なんだろう、思いやっていろいろなことを考えるっていうことは、きっとしないだろうなって。みんながそこにいるから、そういうふうにこのサポートする側はいさせてもらえるのかなって。本当に考えてんのね。思うの。
志村:うーん。なんかこう、相互の関係のように、今伺って思いました。それはお互い違うんだけれども、でもきっと相互の関係が見えない中でおありなんだろうなって、一方通行じゃないですもんね、関わる中で。
萩原:そうそう、あのう、その前に肢体不自由な方たちのね、CPって脳性麻痺の方たちのサポートもしてたことあったんだけど、やっぱり同じで、支援する人たちによって、その人たちの生活がだいぶ変わってくるっていうのかな、とってもそれを感じてね。だからある場所の施設は、サポートする側の人たちに気を遣って、当事者たちが遠慮してるところがあったのね。そういうのって、うーんどうなんだろうなって。向き合える気持ちがみんなあればいいのになって思うけどね。
志村:うーん。今日のこのお話を伺ってると、うりちゃんの根幹の部分は全部繋がってる気がしました。お花に対しても、お祈りに対しても、人との関わり方に対しても、みんな根っこが、大切な部分が同じなんだなって、それをうりちゃんは大切に大切になさってるんだなってことを今伺っていてずっと思ってます。
萩原:そうね。それこそ人間もお花も動物もそうだけど、やっぱり命あるものだから、そこをお互いに思い合って生活できればいいよね。
志村:そうですねー。今のお話を伺っててね、お聞きしたいことがあるんです。このラジオをお聞きになってる方って、いろんな方がいらっしゃいます。若い方から、ご年配の方まで、で、ちょっと夜眠れないなとか、もしくは明日元気に迎えられそうな方もいらっしゃれば、いやちょっと明日きついな月曜日って思う方もいらっしゃるかもしれない。でも今のお話を伺いながら、このメッセージをちょっと一言で伝えていただけると、みなさんの明日の朝の元気の元になるかなって思ったんですけど、なにかありますか?うりちゃん。
萩原:気が利いたことは言えないんだけれども、やっぱり1人じゃないんだよね。今現実1人でいても、やっぱり・・・なんていうのかな、1人だけれども、心の中で1人じゃないって思える心を養ってほしい。私はお寺で1人だけど、やっぱり1人でいる方って多分大勢いらっしゃると思うんだけど、心の持ちようっていうのかな、気持ちの持ち方の切り替えを上手に自分自身でコントロールできるような心を養ってほしい。やっぱり誰かの話じゃないけど、明けない夜はないわけで、明日になればまた朝が来る。今この場で悩んでたり、苦しい思いをしてるけれども、それは一番冒頭でもお話したかもしれないけど、自分事として引き受けて、こういうこともあるよね。だけど心を切り替えれば、もっといろんなことも思えてくるだろうし、うちに秘めて悩まないで欲しいと思うんだよね。人と話しててね、何々のことでとっても後悔してるんだよねって、こういう部分すごい後悔してるって言う話を伺ったりするんだけどね、後悔っていうことは、以前にそういうことがあって、それを後悔してる。でもその以前のときって、その場その場で一生懸命生きてたわけじゃない。確かにその一生懸命生きてたけど、今心に余裕というかゆとりができて、あ、あのときああすればよかった、こうすればよかったっていうふうに思うわけで、だから、そのときそのときで一生懸命してたことを、まあ、後悔して前向きに考えられればいいけれど、後悔して内向きに考える必要はないと思ってるのね。そのときに一生懸命生きたわけだから、それを誇りに思って、切り替えてほしいっていうのかな。
志村:そうですねー。
萩原:うーん。後悔先に立たずじゃないけど、そのとき一生懸命だったんだから、別に後悔する必要はないと思う。そのときの一生懸命だった自分を褒めてあげればいいと思う。
志村:あー、そうですねー。
萩原:あのときはああだったけど、でもしょうがないよねって、あんとき一生懸命だったんだから。
志村:そうだ。
萩原:なんか、前を向いて考える心を養ってほしいと思う。明日は明るいよ。
志村:本当だね。いやなんだか、たくさんのお話を伺ったんだけど、うりちゃんの大事にしてることをお聞きすることができて、本当に幸せでした。
萩原:いえありがとうございます、なんか止めどもない話になってしまって。
志村:あーそんなことないです、そんなそんな、とんでもない。いやーありがとうございます、うりちゃん。
萩原:ありがとうございました本当に。
ARCHIVE